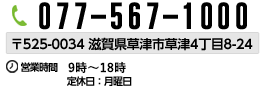ドローン国家資格学科試験に向けての勉強方法

このページでは、二等無人航空機操縦士の学科試験に向けての勉強方法を解説します。
あくまで、抑えておくべきポイントを解説するだけなので、このような問題が出るなどのネタバレなどはありませんのでご了承ください。
まず、試験方法はCBT(Computer Based Testing)と呼ばれるコンピューターを使った試験方法です。試験会場は各都道府県に最低一か所以上あるのでお近くの試験会場で受験できます。受験会場に来ている方は全員無人航空機操縦士の受験者とは限りません。他の資格の受験者の方もおられます。周りは気にせず自身に集中しましょう。試験結果は試験終了のボタンをクリックするとすぐに採点され、結果がわかります。ただし、合格か不合格しかわからないので、仮に不合格だった場合、何点だったのか・どの問題を間違えたのかが一切わかりません。ですが、結果がわかるまで待たされるよりはいいのかなと思います。
おそらくですが、多くの方はCBT試験を受けたことがない方が多いのではないでしょうか。その方達用にCBT試験を主催している「プロメトリック株式会社」は体験版のCBT試験をHP上で公開されています。本番を受ける前に体験することをお勧めします。例題こそ無人航空機とは関係ない問題ではありますが、どのように進めるかはわかるので、本番に焦ることはなくなるかと思います。体験版はPCでしか体験できませんのでご注意ください。以下のURLの下の方にスクロールして頂きますと「CBT体験版」と書かれていますのでそちらをクリックしお試しください。
https://www.prometric-jp.com/examinee/
試験当日は、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要になります。それ以外の荷物は必要ありません。試験時は、携帯電話はもちろん腕時計、筆記用具を含む全ての荷物持ち込み禁止になっています。
試験前に受付を済ませます。試験開始の30分前から15分前までに行いましょう。時間内に受付できない場合、受験することができません。
受付を済ますと基本的に試験開始時間を待たずに試験を行うPCまで案内され、試験開始になります。ですので、お手洗いは受付前に済ますことをお勧めします。お手洗いは試験中も行くことができますが、試験制限時間が惜しいので試験中は行かずに済むようしておきましょう。
試験中の対策としては、以下の方法を試されてはいかがでしょうか。
・間違いやすい傾向として、問題文の読み間違いがあります。ですので、しっかりと問題文を読んで求められている答えが、「正しいもの」なのか「誤っているもの」なのかを判断しましょう。
・問題文を読んで、10秒ほど考えても答えがわからなかった場合はメモ用紙に問題番号を控えて、次の問題に取り掛かりましょう。わかる問題から解いていきましょう。
・画面上部に制限時間が表示されます。焦るのは宜しくはないですが、マイペースに解いていると時間が全然足りません。時間配分を気にしましょう。
・試験は終了時間来るのを待たずに終了することもできますが、時間ぎりぎりまで見直しを行いましょう。後から考えると気づくこともあります。
・時間ぎりぎりまで考えて答えを出して頂きたいですが、もしそれでもわからない場合どれでもいいので回答しましょう。もしかしたら正解しているかもしれません。
試験勉強方法は、現状国家資格が始まったばっかりのため過去問は存在しません。(今後出るかもしれませんが、出ない可能性もあります。)ですので、国土交通省が開示している「無人航空機の飛行の安全に関する教則」を元に勉強しましょう。
特に以下のところは気にしながら勉強すると良いと思います。
・用語がでてくるので、その用語の意味も知っておきましょう。無人航空機の専門用語はもちろんですが、気候などの用語もどんな時にどんな風に吹く風なのかなども知っておきましょう。
・航空法と小型無人航空機等飛行禁止法は比較的似ているのですが、違う法律なので違いを把握し、混同しないようにしましょう。
・出てくる問題はドローンだけでなく、飛行機・ヘリコプターも含まれるので、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
当然ですが、上記に挙げたこと以外の問題も出てきます。出題される問題の割合は私感的にはバランスよく出ている感じがしました。ですので、教則のすべてを覚えるつもりで勉強することを推奨します。
教則の内容を大きく項目分けすると6項目になるのですが、1項目でも勉強していない又は勉強不足の場合落ちると思ってもらってもいいと思います。
ある程度内容を覚えてきたら、友人や家族に問題を出してもらって答えるという方法での勉強もお勧めです。教則を読んでいるだけだと、問題が出たときに答えがなかなかでない時があります。
人にはよると思いますが、私は教則を読んでいて少しでも難しいな・覚えるの大変だなと思ったことはすべて紙に書くようにしました。読むだけでなく、書く動作もしたおかげかテスト時もスラスラと答えが出てきました。
最近ですと、Youtubeに教則の聞き流しの動画を上げている方もおられるので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
本校を受講していただきますと、座学講習はe-ラーニング形式で行うのですが、各項目ごとに章末問題も準備しているので、しっかりと覚えて次の項目を受講できるのでお勧めです。受講から半年は利用できるので、学科試験前にも活用できるのでいいですよね。

国家資格とあってなかなかに難しいと思いますが、ポイントを抑えて合格に向けて勉強していきましょう。応援しております!