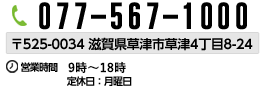レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)実現ついて。続き。
もくじ
それでは先に本ブログにて記していた「レベル4飛行の実現」について、
の続きを、詳細にまとめさせていただきます。
前段の内容はこちら。
その実現の3つの柱である、機体認証制度、操縦ライセンス制度、運航管理に係るルールについて。
1)機体認証制度について
国は無人航空機の機体の安全性を担保するため、機体認証制度を創設します。
ドローンの使用者からの申請により無人航空機の、強度、構造及び性能について国が
定める安全基準に適合するかを設計、製造過程及び現状(実機)について検査し、安全基準
に適合すると認めるときは機体認証を行い、機体認証書を交付することとします。
また国は、設計製造者からの申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について
安全基準に適合し、かつ、設計製造者が適正な製造及び完成後の検査の能力を有すると
認めるときは型式認証を行い、型式認証書を交付することとする。
更に国は機体認証及び型式認証について有効期間を定めることとします。
そして機体認証と型式認証は認証の対象となる無人航空機の飛行形態に応じて
機体に求められる安全性のレベルが異なることから、第三者上空を飛行する
機体であるかどうかの、観点から区分することが適当であり、カテゴリーⅢまでの
飛行を行うことを目的とする機体に対する第一種認証、カテゴリーⅡの飛行を行う
ことを目的とする機体に対する第二種認証に区分することにします。
第三者上空を飛行する機体については、厳密な安全確認が求められることから
型式認証を取得しても、機体認証の検査の一部を省略できるにとどまる。
これに対し、第三者上空を飛行しない(カテゴリーⅡ)機体に関しては、型式認証の
取得により機体認証の検査を全部省力することも可能になります。
また、上記の機体認証と型式認証の検査事務を国のみで行うのは、膨大な数が予想され
キャパシティ上困難と考えられるため、国の登録を受けた民間への検査事務の委託を可能とする
登録検査機関制度が創設されます。
その登録検査機関の登録申請要件として登録申請者において検査事務に従事する者が2名以上であり、
いずれも一定の学科(工学やドローンに関する学科)を習得し、通算して3年以上のドローンの設計、製造過程
及び検査に関する実務経験を有することが必要とされます。
一定の専門的人員の配置が必要であるものの、小規模組織でも登録が可能であることが予想されます。
また登録申請者が、ドローンの製造または輸入を業とする者に支配されていないことが必要とされ検査の中立性
考慮されることになります。
2)操縦ライセンスについて
国は無人航空機を操縦するのに必要な技能(知識及び技能)を有することを証明するために
操縦ライセンス制度(国家ライセンス)制度を創設します。
国は学科試験及び実地試験を行い、身体状態を確認の上、操縦ライセンスを付与することと
します。技能証明の有効期間は3年とし、16才以上から取得可能とします。
国は操縦ライセンスはカテゴリーⅢの飛行を行うために必須とされる一等操縦ライセンスと、
カテゴリーⅡの飛行を行うための二等操縦ライセンスとに区分し、ドローンの種類または
飛行方法についての限定や、身体に応じて条件が付されることもあります。
操縦ライセンスを取得するには一定の欠格事由がないことのほか、原則として身体検査、実地試験
及び学科試験受けて合格する必要があります。
そして、この試験の受験者が多数になることが考えられることから、操縦ライセンスの検査事務を
国が行うことはキャパシティ上困難になるため、国の指定を受けた者への当該試験事務の委託を
可能とする操縦士指定機関の制度が創設されます。
これらは、試験の内容や合否判定の基準の統一性公平性を確保する観点から、全国で一者のみを指定する予定。
同時に一定水準以上の講習を実施することのできる民間機関が国土交通大臣の登録を受けて
無人航空機講習を行う登録講習機関の制度が創立されます。
登録講習機関が行う無人航空機講習を修了した場合、技能証明に必要な学科試験と実地試験の
全部または、一部を免除することも可能とされています。
既存の民間のドローンスクールのノウハウやリソースを操縦ライセンスが導入された後も、有効に
活用するための制度とされており、既に数多く存在している民間のドローンスクールが登録講習機関
の登録申請を行うと予想されています。
また操縦ライセンスの更新(3年に1度)に必要な更新講習についても、登録講習機関と同様に、民間機関が登録更新機関として
の制度も創設される。
3)運行に係わるルールについて
運航管理は無人航空機を安全に飛行させるためのルール(遵守事項)に従うとともに
気象情報や機体の状態等の情報を適切に収集し、目的地までの飛行の安全を確保し
無人航空機の運航の安全を管理する措置です。
国は、以下の項目を法令等に規定し、無人航空機の操縦者に運行管理に係る遵守義務を課すこととします。
カテゴリーⅢの飛行のみ
第三者上空を飛行することによって生じるリスクを低減するためのリスク管理について
、飛行ごとに国の審査を受けることし
その際、操縦者(運行管理者・運行責任者)は
第三者上空を飛行にあたり想定されるあらゆるリスクの分析と評価を行い、リスク
を低減するよう体制を構築し、危害を最小限に留めるための、必要な措置を講じることとします。
カテゴリーⅢ及びカテゴリーⅡの飛行
・他の無人航空機及び、航空機(有人機)との衝突回避のため、無人航空機の飛行計画を
あらかじめ国のシステムに登録する等の方法で通報し、飛行経路や日時等についての
情報を他の操縦者等と事前に共有すること。
また通報された飛行計画について安全に懸念がある場合は国が飛行の日時または、経路の
変更等について指示することが出来ることとし、操縦者は飛行計画や、国からの指示に従い
飛行させることとします。
・飛行実績や機体の整備状況等を確認するための手段として、無人航空機の飛行を行った場合
や整備を行った場合に飛行日誌を作成し、保存することします。
なお飛行の実績は飛行ごとに記録することします。
・操縦ライセンスを有する者がカテゴリーⅡ以上の飛行を行う場合、操縦ライセンスを携帯しなければならないとします。
カテゴリーⅡの飛行のみ
・飛行経路下に第三者が立ち入ることのないよう、補助者の配置等の立ち入り管理措置を講じることします。
・機体認証及び操縦ライセンスの取得の有無や飛行の形態に応じた安全確保措置を講じることとします。
・飛行経路下に第三者の立ち入り又は、その恐れが確認された場合、無人航空機の飛行を停止し、
飛行経路の変更、安全な場所への着陸等の措置を直ちに講じることにより、第三者上空を飛行することの
ないようにすることとします。
事故等の報告に係るルール
すべてのカテゴリーの飛行の操縦者に対して、人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突接触等の事故が
発生した場合に加え、航空機との接近、死傷に至らなかったものの人との衝突接触等が発生した場合など
事故が発生する恐れがあると認められる事態についても国土交通大臣への報告を義務付けることとします。
以上、レベル4飛行実現のための三つの柱である、
機体認証制度、操縦ライセンス制度、運航管理について記させて頂きました。
尚、上記コラムは、2021年3月8日に
「無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会」
の中間とりまとめ資料を参考にさせて頂きました。